
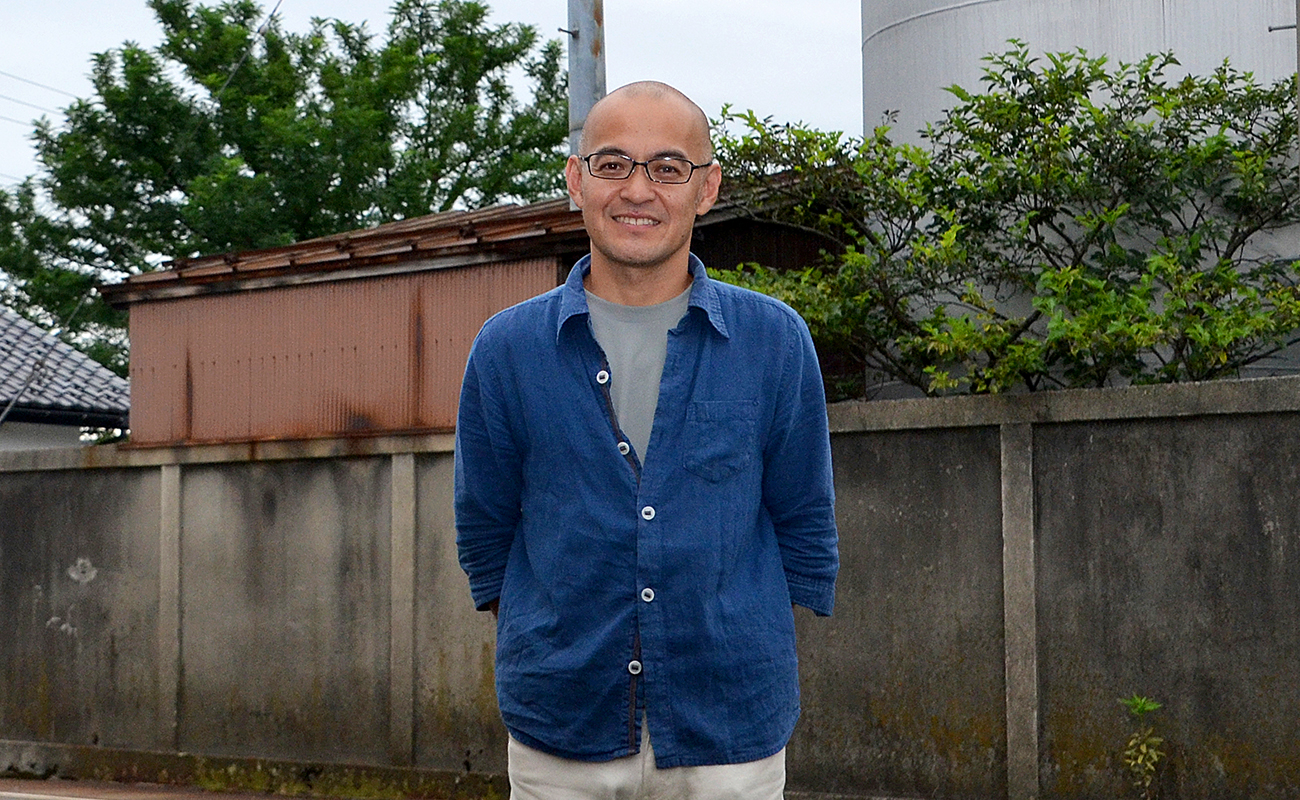

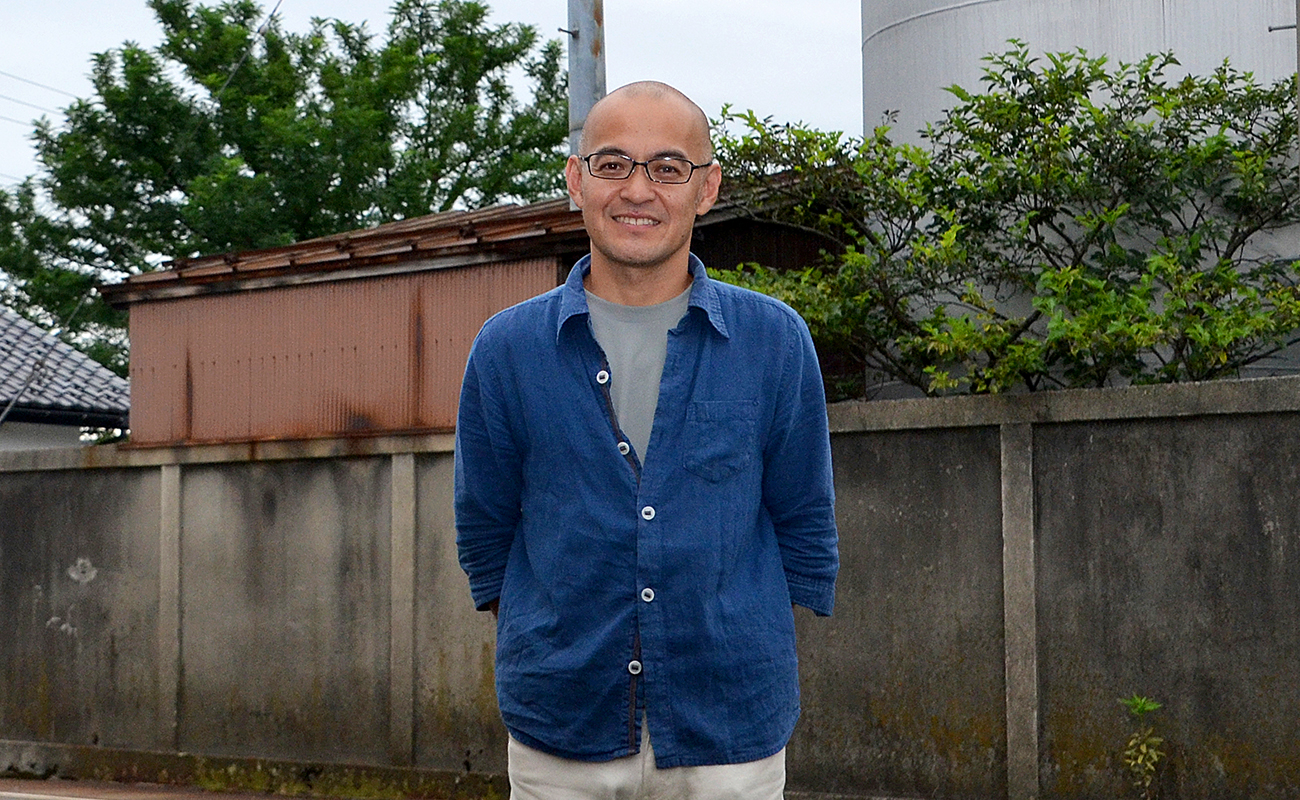
「にいがた酒の陣」に持って行く日本酒は2~3種類です。そのほか毎年、若い人たちに人気なのは、日本酒ベースのフルーツリキュール。今年もぶどうやライチのリキュールをブースに並べる予定です。
 代表取締役社長の松原正人さん
代表取締役社長の松原正人さん
そもそもは長岡街道の街道筋に常陸国小山の庄屋が居を構え、年貢米を使って酒造りを始めたのが出発点。屋号は「常陸屋」だった。

長岡街道は、長岡から妙法寺峠を越えて出雲崎に至る道で、佐渡・相川の金を運ぶ北国街道と、参勤交代の通路・三国街道を結ぶ交通の要衝。比較的積雪が少ないこともあって、多くの人馬が行き交った。
こうした背景もあって造り酒屋は繁盛したらしく、1867年発行の「越後醸酒家一覧」には、常陸屋勝次郎の名があるという。
「常陸屋は代々小山姓を名乗っていたのですが、明治の頃、常陸屋の一人娘が外川家に嫁いだため、酒造りは外川家に引き継がれました。その頃の銘柄は『越之老松』で、現在の主要銘柄『群亀(ぐんき)』も同じ時期に誕生しています」
と語るのは、代表取締役社長の松原正人さん。ついでに『群亀』のいわれについても説明してくれた。
「鶴は千年、亀は万年ということわざがあるように、亀は長寿の象徴です。その亀が群れをなしているのが『群亀』。この酒を飲んで健やかに長生きしていただきたい、との願いが込められているのです」

 代表銘柄は『越後長岡藩』と『群亀』
代表銘柄は『越後長岡藩』と『群亀』
明治時代には順調に業容を拡大したのだろう。中国新聞社による大正7酒造年度『全国醸造家相撲番付』には、製造石数2,552石で「西の前頭」に登場している。その後も破竹の勢いは続く。
大正末期には北海道に進出して釧路に敷島酒造を設立、さらに昭和に入ると中国大陸にも進出を果たした。蘇州に関原醸造公司を設立して、清酒の製造販売を始めたが、日本の敗戦に伴い閉鎖となった。
「現在の関原酒造が誕生したのは1935年です。それまでは個人営業の外川酒造店でしたが、関原酒造株式会社へと改組しました。しかしそれからが大変。
時代は第二次世界大戦に突入して、多くの酒造メーカーが休業を余儀なくされました。国内の食糧事情も逼迫しましたが、関原酒造は一冬も休むことなく酒造りを続けてきました。創業以来のモットー『良酒醸出』は、伝統の寒造りの技で死守されてきたのです」
と、松原社長は激動の時代を振り返った。

 手造りを大事にしつつ、機能的に組まれたライ
手造りを大事にしつつ、機能的に組まれたライ
東京農大の醸造科で学んだ松原さんは、卒業後、東京の製菓会社に勤務。酒造りへの夢捨てがたく、その後、縁あって新潟に赴任してきた。現在は関原酒造の代表取締役であり、製造責任も担っている。
新潟は魚が美味しいから、お酒の造り甲斐がありますねと言うと、「日本酒には魚の旨みを引き立てる成分が含まれているんですよ。生臭さを旨みに変えてくれるんです。ただし、一番上等の魚は築地に行っちゃいますけどね」と、醸造科出身ならではの答え。
「僕が新潟に来たときには120軒も酒蔵があったのに、今は90ですからね」と現状分析にもシビアだ。現代社会に受け入れられる酒造りを見つめ直すと、「辛口でリーズナブルな値段の酒」という結論に達したという。
「お陰さまで『群亀』レギュラー酒は、晩酌酒として親しまれています。量販店にも出荷しているのですが、現状は製造キャパシティが目いっぱいです。
というのも10年ほど前に火災に遭い、貯蔵蔵が全焼してしまいました。そのため、貯蔵スペースが大幅に減ってしまった状態なのです」
そのため、以降は需要の高いものに絞って造っているそうだ。

 需要の高い商品に絞って製造
需要の高い商品に絞って製造
「ここは信濃川の伏流水が豊富で、水に恵まれているんです。でも当社は高台にあるので、冬場は足りなくなることもあります」と、水事情について語る。
造っているのは甘辛のバランスのとれた酒。「障りなきこと水の如し」をモットーに、きれいな酒質の酒を目指しているという。
「日本酒の良さは食事に合うことだと思います。うちは昔ながらの辛口でふくよかな酒、きれいな酒質を良しとしてきました。昔からのものを受け継いで、地元のために造る、お客様のために造るという基本姿勢を貫いています」
また新しく開発したものに日本酒ベースのフルーツカクテルがある。ブドウの果汁感たっぷりの「白ぶどうのお酒」と、ライチの果汁感に満ちた「ライチのお酒」だ。
いずれもアルコール度数が低く、さっぱりとして飲みやすいのが特徴。「よく冷やして、ストレートまたはロックで楽しんでほしいですね」とのこと。
以下は蔵元お勧めのお酒だ。

60%まで磨いた国内産米を使用。雪深い越後長岡の厳冬期に、丹念に仕込まれた。やや辛口で膨らみのある味わい。アルコール度数は15%。

江戸中期の創業以来、愛され続けている伝統の銘柄。新潟清酒にふさわしい淡麗で辛口の味わいは飲み飽きしない。冷酒から熱燗までOKで日々の晩酌を豊かにする。

独自の技術で造り上げた砂糖不使用のリキュール。巨峰果汁の自然な甘さと日本酒のコクの相性は抜群。アルコール度数9%、よく冷やしてどうぞ。
取材/伝農浩子・文/八田信江